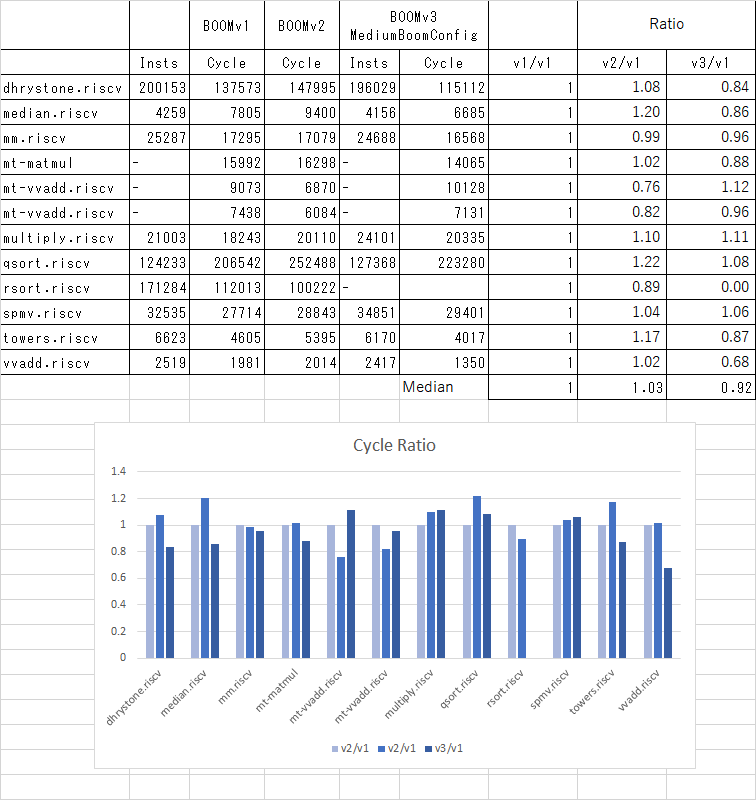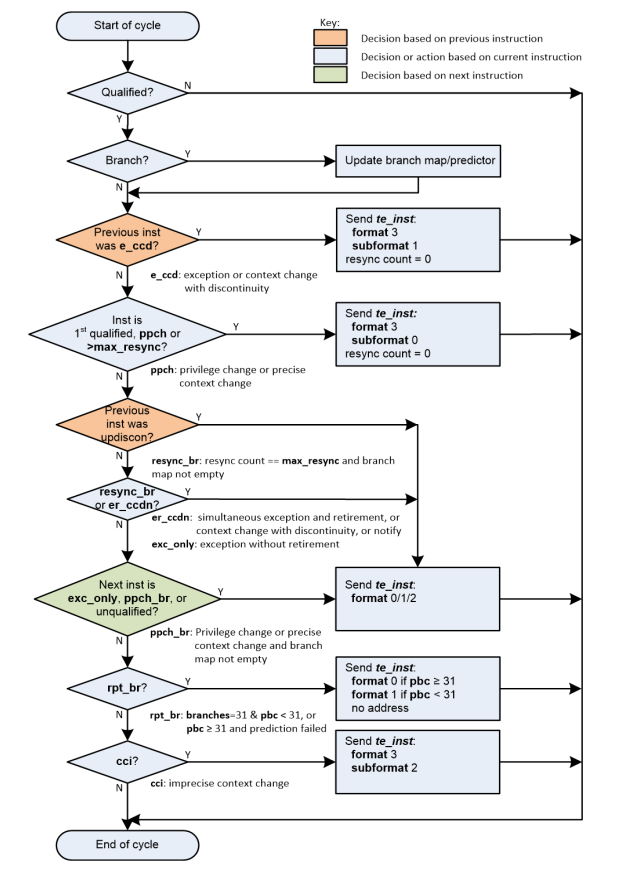RISC-VのオープンソースプロセッサBOOMv3(SonicBOOM)が公開されているが、シミュレーションを行うためにはChipyardの環境を用意するのが原則になっているようだ。
SonicBOOMv3のリポジトリ事態にCoremarkは入っていないようなので自分でバイナリを構築する必要があるらしい。が、CoremarkのRISC-V向けビルド環境があるらしい。
pk向けのバイナリとBaremetalのバイナリの両方が作れるらしい。これをダウンロードしてビルドしておけばよいのか。
git clone https://github.com/riscv-boom/riscv-coremark.git cd riscv-coremark git submodule update --init --recursive ./build-coremark.sh
一応ログを出したいので、BOOMをログ付きでビルドしておく。
src/main/scala/common/parameters.scala
diff --git a/src/main/scala/common/parameters.scala b/src/main/scala/common/parameters.scala index 1a0c25fd..8d7c910c 100644 --- a/src/main/scala/common/parameters.scala +++ b/src/main/scala/common/parameters.scala @@ -92,7 +92,7 @@ case class BoomCoreParams( clockGate: Boolean = false, /* debug stuff */ - enableCommitLogPrintf: Boolean = false, + enableCommitLogPrintf: Boolean = true, enableBranchPrintf: Boolean = false, enableMemtracePrintf: Boolean = false
で、そのままVerilatorのバイナリに流して実行する。CMK値は 3.83CMK/MHz となった。
cd sims/verilator/ make CONFIG=MediumBoomConfig ./simulator-chipyard-MediumBoomConfig +verbose ../../riscv-coremark/coremark.bare.riscv >& coremark.medium.riscv.log
全部ログがcoremark.medium.riscv.logに出てきてしまうので、grepして抽出する。
grep -v ^3 coremark.bare.riscv.log
using random seed 1592581205
This emulator compiled with JTAG Remote Bitbang client. To enable, use +jtag_rbb_enable=1.
Listening on port 55449
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size : 666
Total ticks : 2608224
Total time (secs): %f
Iterations/Sec : %f
ERROR! Must execute for at least 10 secs for a valid result!
Iterations : 10
Compiler version : GCC9.2.0
Compiler flags : -O2 -mcmodel=medany -static -std=gnu99 -fno-c3 0x00000000800025b4 (0xdf7d)
ommon -nostdlib -nostartfiles -lm -lgcc -T ../riscv64-baremetal/3 0x00000000800025b4 (0xdf7d)
link.ld
Memory location : Please put data memory location here
(e.g. code in flash, data on heap etc)
seedcrc : 0xe9f5
[0]crclist : 0xe714
[0]crcmatrix : 0x1fd7
[0]crcstate : 0x8e3a
[0]crcfinal : 0xfcaf
Errors detected
*** PASSED *** Completed after 2659834 cycles
[UART] UART0 is here (stdin/stdout).
ついでにMegaBoomConfigも試してみる(最大構成)。CMK値は 5.33 CMK/MHz となった。
./simulator-chipyard-MegaBoomConfig +verbose ../../riscv-coremark/coremark.bare.riscv >& coremark.mega.riscv.log
using random seed 1592619488
This emulator compiled with JTAG Remote Bitbang client. To enable, use +jtag_rbb_enable=1.
Listening on port 59775
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size : 666
Total ticks : 1873606
Total time (secs): %f
Iterations/Sec : %f
ERROR! Must execute for at least 10 secs for a valid result!
Iterations : 10
Compiler version : GCC9.2.0
Compiler flags : -O2 -mcmodel=medany -static -std=gnu99 -fno-c3 0x00000000800025b2 (0x6298) x14 0x0000000000000000
ommon -nostdlib -nostartfiles -lm -lgcc -T ../riscv64-baremetal/3 0x00000000800025b4 (0xdf7d)
link.ld
Memory location : Please put data memory location here
(e.g. code in flash, data on heap etc)
seedcrc : 0xe9f5
[0]crclist : 0xe714
[0]crcmatrix : 0x1fd7
[0]crcstate : 0x8e3a
[0]crcfinal : 0xfcaf
Errors detected
*** PASSED *** Completed after 1917263 cycles
[UART] UART0 is here (stdin/stdout).
ベンチマークをすべて流してみても、全体的にMegaBoomConfigはMediumBoomConfigよりも高速だ。1.5倍くらいのサイクル性能向上かな。